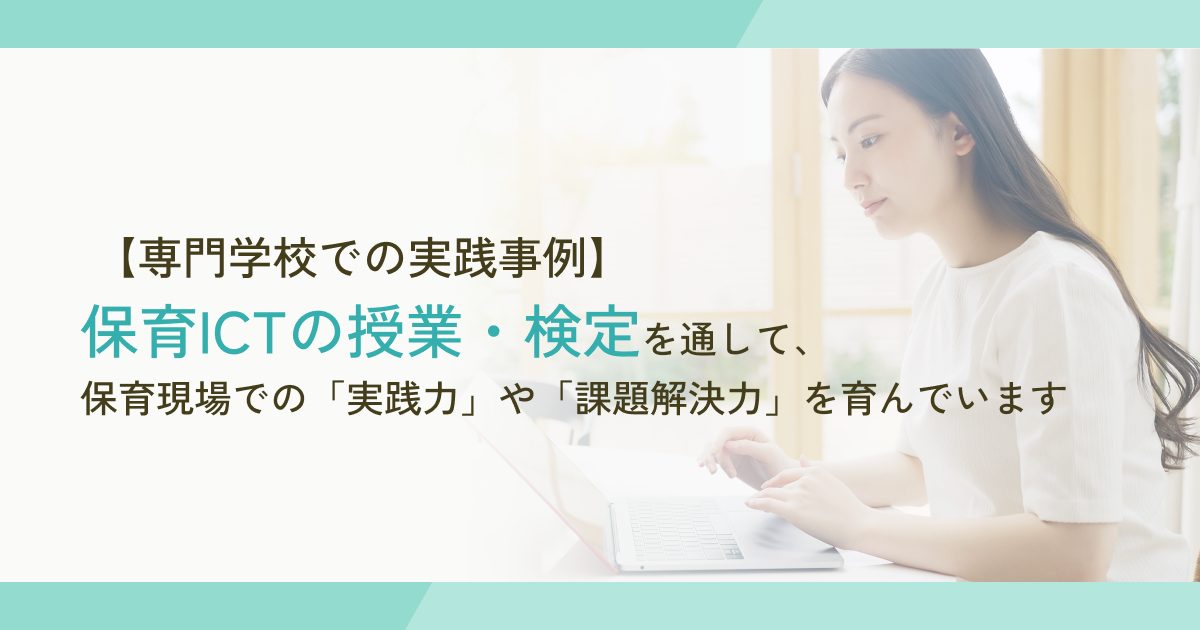はじめに
近年、保育現場でもデジタル化が進み、日々の業務にICT(情報通信技術)の活用が欠かせなくなってきました。こうした時代の流れを受けて、筑波研究学園専門学校では、保育士を目指す学生が現場で即戦力として活躍できるよう、ICT活用に関する授業と、保育ICT協会が実施する検定制度を積極的に導入しています。
本記事では、導入の背景や授業内容、保育ICT協会による検定制度の特徴、さらに学生や保育現場に与えている影響について、授業担当教員へのインタビューを交えながらご紹介します。保育施設の皆さまや、他の保育士養成校の先生方にとっても、実践的な人材育成のヒントとなれば幸いです。
筑波研究学園専門学校(TIST)
話を聞いた学部:こども未来学科(保育士・幼稚園教諭養成課程)・児童教育専攻科(小学校教諭・養護教諭養成課程)
定員数:255名
所在地:茨城県土浦市上高津1601
特徴:
・「職業実践専門課程」認定
・DX(デジタルトランスフォーメーション)カリキュラム導入
・広大なキャンパス・充実した学習設備・高い就職率

導入の背景――なぜ今、授業で保育ICTを学ぶのか
保育現場では、業務の効率化や保育の質の向上を目的として、ICTの活用が急速に進んでいます。こうした変化に対応するため、筑波研究学園専門学校では、ICTに関する授業や「保育ICT検定」を導入しています。
これらの取り組みは、保育現場で求められるICTリテラシーを実践的に身につけることを目的としており、保育業務のデジタル化や情報の適切な管理・共有に対応できる力の習得につながります。
本校では、知識の習得だけでなく、現場で即戦力となる実践力の育成を重視し、ICTを活用した保育に自信をもって取り組める人材の育成を目指しています。
保育現場におけるICT活用を知ったきっかけは、学科開設当初からお世話になっている法人で「コドモン」が実際に導入・活用されていたことでした。そこから、保育ICT検定やコドモン検定の存在を知ることとなり、さらにコドモン社へ問い合わせたところ、保育ICT推進協会をご紹介いただき、導入に向けた具体的な検討が進むようになりました。
授業の様子――実践的な学びの現場
授業では、実際の保育現場で導入が進む保育ICTシステム(コドモン)を活用し、記録や連絡帳の作成、写真・動画の管理など、現場の業務をリアルに再現した演習を行っています。単なる操作方法の習得にとどまらず、「保育ICTが保育の質や子どもたちの成長にどう影響するか」といった視点も重視。学生たちはグループワークやディスカッションを通じて、現場での課題解決力やコミュニケーション力も養っています。

学生・現場への影響――広がる可能性と課題
学生からは、「現場で実際に使われているツールを体験することで、保育におけるICT活用の具体的なイメージがつかめ、実践力が高まった」「保育ICTを取り入れることで、事務作業が効率化され、その分子どもと向き合う時間を確保できる点に魅力を感じた」といった、前向きで意欲的な声が多く寄せられました。
一方で、「操作を覚えるために反復学習の機会は必要だと感じた」といった意見もありました。
まとめ
筑波研究学園専門学校におけるICT授業および保育ICT検定の取り組みは、デジタル化が進む保育現場を見据え、実践力と柔軟な対応力を備えた保育士の育成を目指す、新たな学びのモデルといえます。
今後も、地域や産業界との連携を深めながら、こうした先進的な取り組みが全国の保育教育に広がっていくことが期待されます。
取材協力:筑波研究学園専門学校
(※記事内容は取材時点のものです)