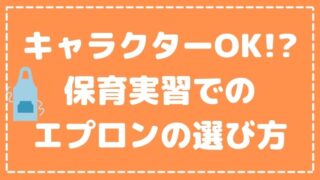これから初めての保育実習を迎える方は、可愛い子どもたちと触れ合える楽しみと同時に、緊張や不安な気持ちもあると思います。
なかでも、服装や持ち物は、どのようなものを準備すればいいのか、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
保育実習中の服装や持ち物は、実習先の保育士や保護者、子どもたちからの印象をよくするためにも大切なものです。
過去に保育実習の経験がある筆者も、同じように最初の持ち物にはとても慎重になりましたし、不安にもなりました。
そこで今回は、保育士の目線から保育実習にふさわしい服装や、持っていくと便利な持ち物についてご紹介します。
通勤時は基本的にスーツで
保育実習の通勤時は、基本的にはスーツを着用しましょう。
保育士のなかには、保育時の私服でそのまま通勤する人もいますが、実習生が同じようにしていいとは限りません。実習生であるという立場をわきまえ、たとえ私服通勤がOKであっても、少なくとも初日はスーツで登園しましょう。
実習前のオリエンテーション、または実習初日に、スーツから実習着へ着替えられる場所があるかどうかを実習先の保育士に確認するようにしてください。
ただし地域や園の環境によっては保育時の服装で通勤可能な場合もあります。心配であればオリエンテーションなどで、そもそもの通勤時の服装について聞いてみましょう。
保育実習中の基本の服装は?
保育中は、どのような服装がふさわしいのでしょうか。
まずは、基本の服装から紹介します。
シャツ
基本的には、重ね着ができるような薄手のTシャツやポロシャツです。
Tシャツは、胸元が大きく開いているものは避けましょう。かがんだときなどに下着が見えてしまうことがあります。
色は、シンプルな白やグレー、黒などのモノトーンがおすすめです。黒は威圧的な印象を与えるので避けられがちですが、エプロンを付ければ柔らかい印象になるため、さほど気にしなくても大丈夫です。
ズボン
子どもと一緒に動き回ったり、何度も立ったり座ったりしますのでズボンを履きましょう。園によって指定されるところもありますが、ジャージかチノパンが好ましいです。
色は、シャツと同じようにモノトーンが落ち着いて見えます。
ジャージはロゴ入りや柄ものなどさまざまですが、あまり華美なデザインのものは避けましょう。通っている学校の指定ジャージを持っている場合は、実習でそれを使うことをおすすめします。
スカートやフレアパンツなどのひらひらするものは、思わぬ事故を招いてしまうことも考えられるので、絶対にNGです。
エプロン
上からすっぽりとかぶることができて長さが太もものあたりまであるような、フルエプロンかスモッグがおすすめです。
保育の現場は、汚れやすい活動が多いため、広い範囲を覆ってくれるエプロンが適しています。
園からの指定がなければ、キャラクターものも多くあるので、子どもとの話題づくりにキャラクターものを選んでもいいでしょう。
ただし、エプロンは保育実習期間だけでなく、就職してからも使うものです。
キャラクターものを避けている園もありますので、無駄な支出をしたくないという場合は、先を見据えて動物が描かれている程度の柄ものを選んでおくという手もあるでしょう。
靴
保育実習で履く靴は、動きやすさを意識しましょう。
また、靴も服装と同様に清潔感が大切です。子どもと活動する中で汚れてしまった場合は、汚れを拭き取ったり、洗ったりして常にキレイな状態にしておきましょう。
中履き
中履きは、足の甲にゴムがかかるタイプのバレエシューズなどがおすすめです。
筆者が働いていたときも、バレエシューズを使っていました。脱ぎやすく、そして履いているときは脱げにくいことが特徴です。
0〜1歳児クラスは、子どもたちが靴をはかずに過ごすことが多く、保育士も部屋の中では靴を脱いで過ごします。そのため、部屋を出入りするたびに靴を脱いだり履いたりします。脱ぎにくいものは、行動のしにくさに繋がります。
また、2〜5歳クラスでは活発な活動が多く、履いているときに脱げやすい靴では子どもと全力で遊ぶことができません。
そのため、脱ぎやすく、また活動中は脱げにくいバレエシューズを中履きに選ぶといいでしょう。
外履き
外履きは履きやすいものを選びましょう。
屋外での活動も多い保育現場。遊びだけではなく、保育実習中に避難訓練もおこなわれる可能性があります。
保育士は子どもよりも早く靴を履いて、指示を出したり子どもの靴の着脱を手伝ったりしなければなりません。そのため、外履きの履きやすさは選ぶときの大切なポイントになります。
普通の運動靴で構いませんが、毎回靴紐をほどいたり結んだりしなくてもいいように調節しておくか、靴紐部分がゴムになっているタイプの運動靴もおすすめです。
帽子・アームカバー
屋外で活動したり散歩に出かけたりするときには、日差しが強い日もあります。そんなときのために、必ず帽子を用意しておきましょう。
風が強い日は飛ばされてしまうこともありますので、しっかり顎で固定できる紐付きのものを選びましょう。日差しをカットできるような、ツバの広いものがおすすめです。
また、日焼けから肌を守るために、必要に応じてアームカバーも用意しておくといいでしょう。
季節に応じた服装の注意点
保育実習を行う季節によって、半袖や長袖など服装も変わります。どんな服装をするとしても、子どもの安全を第一に考える必要がありますので、そのあたりについても言及しています。参考にしてみてくださいね。
春・秋の服装
季節の変わり目なので、服装の選び方が難しいですよね。かといって、前開きのカーディガンを羽織るようでは動きづらくなってしまい、あまり好まれません。
筆者がよくしていた服装は、半袖Tシャツ+長袖Tシャツか、半袖ポロシャツ+長袖Tシャツの重ね着です。
暑ければどちらかを脱いで調節することができます。また、カーディガンのようにひらひらしないので、子どもにあたる心配もありません。
それでも寒い場合は、薄手のトレーナーをTシャツの上から着るようにしましょう。
夏の服装
夏は露出が多くなりがちですが、下着が見えないように配慮をしましょう。トップスは胸元が開きすぎないようにし、ボトムスは長スボンか、膝よりも下のハーフパンツにします。
幼児クラスになると、一緒にプールに入る機会もあるので水着の用意も必要かと思います。その場合は、なるべく露出がないように運動用の水着の上から着られるラッシュガードを用意するようにしましょう。
また、裸足になるためサンダルの用意も必要になります。ビーチサンダルやクロックスなど、すぐに脱げるタイプが適しています。
詳しくは、実習園から持ち物について提示があると思いますので、そちらを参考にしたり、確認をとったりしましょう。
冬の服装
冬はトレーナーを選ぶようにしましょう。
フードのついているパーカーは、子どもが引っ張ってしまう心配があるため多くの園で禁止されています。また、春秋と同じように前開きのカーディガンはあまり好ましくありません。
そのため、動きやすくて危険にも配慮したトレーナーを選ぶのがベストです。
ただし、どの季節でも言えることですが、室内で子どもと過ごしていると暑くなる場合が多いです。冬でも長袖Tシャツで十分というケースもありますので、まずは数日自分が過ごした体感で服装を考えてみてくださいね。
保育実習のカバンの選び方
実習ノートや着替え、園によってはお弁当を持っていくところもあると思います。最低限A4サイズが入るカバンを選びましょう。
トートバッグやショルダーバッグ、リュックなどさまざまなタイプがありますが、実習によっては一緒に遠足に行く可能性もあります。
そのため、リュックをひとつ用意しておくと便利です。
こちらも服装同様に、シンプルで柄のないタイプのものを選ぶようにしましょう。
保育実習の持ち物について
次に、保育実習に必要な持ち物について紹介していきます。
筆記用具・メモ帳
保育実習中の大事なことをメモしておくために筆記用具とメモ帳は必ず用意し、エプロンのポケットの中に入れておきましょう。
なお、実習園によっては、子どもの安全を考えてペンをエプロンのポケットに入れることを禁止している場合もありますので、持ち歩いていいのかどうか、確認してください。
文房具
壁面製作やその他製作物のお手伝いをすることがあります。ハサミ、カッター、のり、ホッチキスは用意しておくと便利です。
保育実習日誌
保育実習日誌は、絶対に忘れてはいけないもののひとつです。
朝に、前日の保育実習日誌を提出し、退勤時に返却してもらえることが多いかと思います。実習園によっては子どものお昼寝中に書く時間を設けてもらえる場合がありますので、提出するファイルとは別に数枚カバンに入れておくとよいでしょう。その日あった出来事を思い出しながら、丁寧な文字と文章を心がけて記入してくださいね。
ティッシュ・ハンカチ
子どもが鼻水や鼻血を出してしまったときにサッと拭けるよう、ポケットティッシュは常にエプロンの中に入れておきましょう。
保育現場にもティッシュは置いてありますが、ポケットティッシュを持っていればすぐに対応することができます。
また、ハンカチは日常生活で必須です。手を洗う場面、そして避難をするときに口にハンカチを当てるよう子どもに指導している園も多いです。
実習生も、子どもから見ると立派な先生なので、お手本である先生がハンカチを持っていないと大変です。忘れずに持つようにしましょう。
着替え
保育中は、製作活動や子どものよだれ、吐物などで汚れたり、動き回って汗をかいたりと保育士自身も着替えが必要な場面が多々あります。
衣服上下、エプロン、靴下、夏は下着の着替えも1セットずつ持っていくと困らないでしょう。
飲み物
保育中「水分補給していいよ」と言われるときがあります。
夏場は特に、子どもが家から水筒を持ってくる園も多く、保育士自身も、自分の体調管理に気をつけ、適宜水分補給をしています。
事前のオリエンテーションなどで確認し、必要があれば水筒を用意しておき、しっかり水分をとるようにしましょう。
保育実習前に準備しておくと便利なもの
最後に、持ち物とは別に保育実習前に準備しておくと便利なものを紹介します。
手遊び
手遊びは、保育士がよく使う技術のひとつです。
ちょっとした待ち時間や絵本を読む前、話をする前など子どもとコミュニケーションを取りながら注目してもらいたいときに大活躍です。知っている手遊びならまわりの保育士も参加しますし、子どもも気に入れば何回もやってくれますよ。
手遊びは、数を知っていればいるほどいろいろな場面で役立ちますが、保育実習でおすすめするのは以下の場面で楽しめるような手遊びです。
・活動がはじまる導入として使える手遊び(はじまるよ)
・季節の手遊び(小さなはたけ, クリスマスの手遊び など)
・食べ物系の手遊び(たこ焼きの作り方の手遊び)
・ちょっとふざけた手遊び(りんごゴロゴロ)
子どもが笑ってくれる姿を想像しながら覚えてみてください。楽譜がある場合は音程をしっかりとれるようにしておきましょう。
絵本
実習が進むと保育士から「何かやってみる?」と提案されることがあります。
絵本を読むというだけでも、子どもとかかわる貴重な経験です。どんどん積極的にやっていきましょう。園にある絵本を借りてもいいですが、自分で発達に応じたものを何冊か用意しておくと事前に練習しておけるので安心です。
手袋シアター・エプロンシアター
縫い物が得意な人は手袋シアターやエプロンシアターに挑戦してみるのもいいですね。
筆者は、指の先にいろんな色のお化けがついた手袋シアターを用意したことがあります。
手をグーにすると隠れて、パーにするとお化けが現れる仕組みです。動きを早くするとお化けが出てきたり隠れたりして見えるので、子ども達も楽しんでいました。
手袋シアターは、エプロンの中に小さくして忍ばせておけるため、気軽に取り入れることができます。
エプロンシアターは少し高度ですが、子どもがそのあと自分のごっこ遊びに取り入れてくれることもありました。
どちらも保育現場では一般的なシアターなので、子どもも慣れていて安心して見てくれることでしょう。
ペープサート
ペープサートは、裏表を利用すると簡単なクイズができるグッズです。本格的な劇のようにしても楽しめるので、おすすめのグッズのひとつです。
紙と割り箸(棒)があれば簡単に作れるところも魅力的です。絵本のほかに、もうひとつ必殺技として用意しておくのはいかがでしょうか。
子どもの安全を意識して服装や持ち物を整えよう!
保育現場は、子どもの活動が第一です。また、安全も守らなければなりません。
そのことを常に頭に置いて、保育実習の服装はシンプルに動きやすさを重視して選ぶようにしましょう。
持ち物も、ある程度事前に揃えておくことで、忙しい保育実習中に慌てて準備するという事態を避けることができるでしょう。実習先の保育士にも、「この実習生はやる気があるな」と思ってもらえるかもしれませんね。
学校や実習園から言われていることと、今回紹介したことを参考に準備をして、ぜひ有意義な保育実習になるようにしてください。